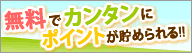忍び村のお金畑ーーしのびの世界
アクセス解析
管理画面

10円があたるスクラッチが毎日やっている。
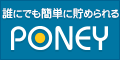



トラフィックエクスチェンジ
リードメールはここが強い
プレジデントメール
NobleMail
エックスメール
ペガサスメール
speedtraffics
リードメール
アクセス宣伝隊長
SugarMail
ABCリードメール
キングオブリードメール
流石めーる

10円があたるスクラッチが毎日やっている。
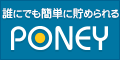



トラフィックエクスチェンジ
| オレンジトラフィック |
| アップアクセス |
| EX-SURF |
| 【もっとアクセスUP】 |
| begood.jp |
| トラフィックエクスチェンジ |
| BuleCloud |
| 三ツ星トラフィックエクスチェンジ |
| BCトラフィック |
| トラフィックNo.1 |
| Traffic-BSJ |
| TRAFFIC MAKER |
| オレンジモバイル |
| トラフィックエクスチェンジ<アクセスアップ> |
| traex |
| 小山商店.com |
| トラフィックジャングル |
| adpierce |
| farm3 |
リードメールはここが強い
プレジデントメール
NobleMail
エックスメール
ペガサスメール
speedtraffics
リードメール
アクセス宣伝隊長
SugarMail
ABCリードメール
キングオブリードメール
流石めーる
counter
最新コメント
[02/27 Surveys]
[03/30 gogom]
[05/18 Backlinks]
[08/26 NONAME]
[07/06 Maddydog]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
アクセス解析
フリーエリア
My file
myfile
いっぱいなPoint
自動車noronoro
占いメイキー
これは何だ
注目のリンク集
tooless
交通量観察
人類滅亡時計
看護師求人
フレンボ
フレンボのお金畑
Books12
Books
携帯でお小遣い
少ないお小遣い
太陽光発電てかてか
脳梗塞からどこへ
空調服
忍者村のお金畑
トラフィックエクスチェンジ
シーサー村のお金畑
いっぱいなPoint
自動車noronoro
占いメイキー
これは何だ
注目のリンク集
tooless
交通量観察
人類滅亡時計
看護師求人
フレンボ
フレンボのお金畑
Books12
Books
携帯でお小遣い
少ないお小遣い
太陽光発電てかてか
脳梗塞からどこへ
空調服
忍者村のお金畑
トラフィックエクスチェンジ
シーサー村のお金畑
カテゴリー
宣伝
 Perlによるシステム管理
Perlによるシステム管理デイビッド・N. ブランク‐エデルマン
オライリー・ジャパン 刊
発売日 2002-07
PerlといえばWebサーバー上で動くCGIの代表的なプログラミング言語と思われているが、もともとはシステム管理や運用作業のツールとして生まれた、インタプリタ型のスクリプト言語である。CGI関連のPerlの参考書はたくさんあるが、システム管理について書いた本はほとんどない。
本書は、プログラミング言語Perlを使用してさまざまなシステム管理に対応する方法を解説したものである。Perl・システム管理の初心者からベテランの技術者まで、幅広い読者を対象としている。各章では、システム管理業務の中でも著者がとくに重要と考える分野を取り上げている。
1章では、Perlプログラムをより安全に記述するためのガイドラインについて、2章では、マルチプラットフォームのファイルシステムを正しく使用する方法やdisk quotaを制御する方法について、3章では、UnixとWindows NT/2000の異なるOS上でユーザーアカウントがどのように扱われるかについて、4章では、Macを含む3種類のOSのプロセス制御の違いや、ファイルネットワーク操作の追跡について、5章では、TCP/IP上のネームサービスとPerlによるサービスの管理について、6章では、LDAPやADSIといったディレクトリサービスの紹介とPerlによる利用方法について、7章では、DBIとODBCの2つのSQL DBフレームワークの説明と利用例について、8章では、Perlを用いたメールの送信や基本的な解析の説明とUCEなどのアプリケーションについて、9章では、ログファイルについて、10章では、セキュリティとネットワーク監視について、それぞれ解説している。各章の末尾には、使用したPerlモジュールの一覧と参考文献が示されている。
本書は、システム管理の経験者や当該分野に興味のある読者、なかでもLinux、FreeBSDを含むUnixとWindows NT/2000サーバーが混在する環境で両方のサーバーを管理しなければなならない読者におすすめしたい。(大塚佳樹)
さらに詳しい情報はコチラ≫
PR
 入門Perl・Tk―Perlで簡単GUIプログラミング
入門Perl・Tk―Perlで簡単GUIプログラミング須栗 歩人
秀和システム 刊
発売日 1999-12
Perl/Tkの数少ない入門書 2001-12-28
Tkモジュールモジュールを使うプログラミング言語としてはTcl/TKが非常に有名であるがPerlでの使用も可能である。GUIのアプリケーションを作成したくて、なおかつPerlの知識を持っている人にはよい入門書となることでしょう。
さらに詳しい情報はコチラ≫
[PR]林なつき
 Perlベストプラクティス
PerlベストプラクティスDamian Conway
オライリー・ジャパン 刊
発売日 2006-08-24
日頃のPerlスタイルの復習と発展学習に 2006-10-22
Perlでコーディングする際のプラクティスが項目に分けてまとめられています。著者の長年の経験の積み重ねによって得られたプラクティスということで、勉強に部分も多いです。
特に、Perl 5.8以降でのプラクティスが多数まとめられているので5.003以前のバージョンから入った私には、「おぉ、そんな機能変更が!」と気づかされる点が多かったです(perldocを読んでいないだけですが)。これまでmapなどの反復リスト操作はforeachなどで済ましていたのですがmapの方が効率がいい、など日頃のコーディングの見直しが図れると思います。
ある程度Perlでコーディングしたことがある人におすすめ。参考書というより復習、発展学習といったところだと思います。
さらに詳しい情報はコチラ≫
[PR]産み分けの方法
 Perlクックブック〈VOLUME1〉
Perlクックブック〈VOLUME1〉トム クリスチャンセン /ネイザン トーキントン
オライリージャパン 刊
発売日 2004-09
Perlプログラマ必携本(ご存知でしょうけど) 2005-03-01
プログラミングをしていると遭遇する思考の迷路。
解法をサンプルコードと共に丁寧に解説しています。
ロジックは他の言語にも役立つことがありました。
結構楽しく読めました(?)
用語解説などは無いので基本的なPerlの知識が必要かも知れません。
また参考情報として同じオライリーの「プログラミングPerl改訂版」が頻繁に紹介されています。
併せて持っておくと良いでしょう。
私は持っています。
さらに詳しい情報はコチラ≫
[PR]お見合いノウハウ
 Perlネットワークプログラミング―ソケットの使い方からクライアント/サーバーシステムの開発まで
Perlネットワークプログラミング―ソケットの使い方からクライアント/サーバーシステムの開発までリンカーン スタイン
ピアソンエデュケーション 刊
発売日 2002-12
Perlの普及はインターネットの普及と大いに重複している。従って、ほとんどのPerlによって書かれたプログラムはインターネット経由でサービスを提供している。本書はサブタイトルに「ソケットの使い方からクライアント/サーバーシステムの開発まで」とあるように、ネットワーク上でのPerlの活用に必要な知識をほぼすべて網羅している。
本書は、4つのパートからなり、それぞれ「基礎」「一般的なサービスのクライアントの作成」「TCPクライアント/サーバーシステムの開発」「応用」となっている。「パート1 基礎」では、ファイルハンドルなど入出力の基礎、プロセス、パイプ、シグナル、Berkeleyソケット、Ping等のネットワーク分析ツール、TCPプロトコルとソケットオプション、IO::Socket API等、Perlを使用するうえで不可欠な知識がまとめられている。
「パート2 一般的なサービスのクライアントの作成」では、BerkeleyソケットAPIに基づき、Net::FTP、Net::Telnet、Net::SMTP、MailTools、MIME-Tools、Net::POP3 API、Net::IMAP::Simple API、Net::NNTP、LWP、HTML::Formatter API、HTML:TreeBuilder API、HTML::Parserといった、Perlを使用する際に一般的に使われるモジュールと、それらに対応するサービスを解説している。
「パート3 TCPクライアント/サーバーシステムの開発」で解説しているのは、「精神分析医サーバー」を例として、並行技術としてのフォークサーバー、inetdデーモン、マルチスレッド、多重化アプリケーション、非ブロックハンドル、システムログ、プリフォークとプリスレッド、IO::Pollといった、サーバー側の機能である。「パート4 応用」では、一般的なTCP上では扱わない部分、つまりTCP緊急データ、UDPプロトコルとUDPサーバー、ブロードキャスト、マルチキャスト、UNIXドメインソケットについて取りあげている。
少なくとも、プログラマーレベルで必要な知識は十分に盛り込まれている。問題解決のためのリファレンスとして、十分に機能してくれるだろう。 (大脇太一)
perlプログラムの良い参考書です! 2004-07-19
ネットワーク関係のいろいろなプログラムがPerlで書かれています。
最初にUNIXの入出力・プロセス・シグナル・パイプの説明があり、ソケット、そしてTCPのサーバ・クライアントシステムの説明と続きます。
ネットワークプログラムのアーキテクチャが詳細に書かれており、また密接にPerlと連携して書かれているので、Perlの勉強にもなると思います。
Perlは比較的簡単に実行できる言語なので、例文を打ち込んですぐ試して確認することで理解が深まるのではないでしょうか。
Perlをある程度経験している人にすごくお勧めです!!
さらに詳しい情報はコチラ≫